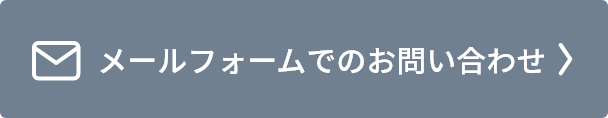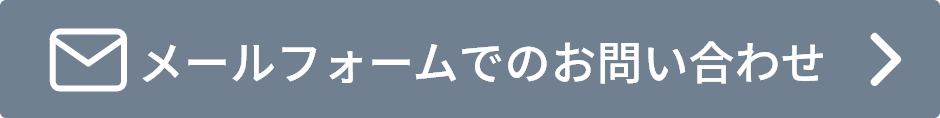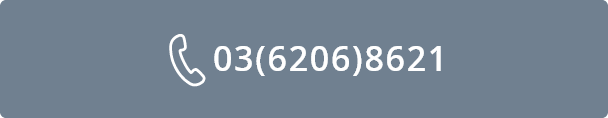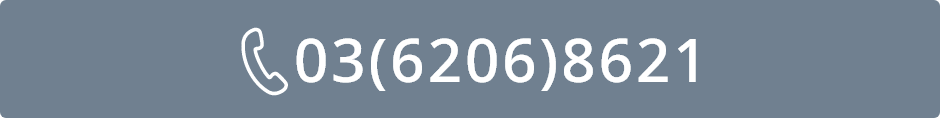活動情報
「現場から未来へ。物流を変える、挑戦の集い。」改善ソリューション委員会成果発表会
2025.08.05
~物流の未来を拓く、現場からの挑戦~
2025年7月30日(水)、富士ソフトアキバプラザにて「改善ソリューション委員会成果発表会」が開催されました。会場には多くの観客が集まり、物流業界の課題と可能性に向き合う熱気に包まれました。
冒頭では、一般社団法人日本3PL協会の加藤専務理事より開会のご挨拶があり、続いて、改善ソリューション委員会の副委員長である二宮修次氏(株式会社ハイペリオン 常務取締役)より、2025年度の委員会活動の概要とその背景についてご説明いただきました。
さらに、委員長であるセンコーグループホールディングス株式会社 専務執行役員 藤田浩二氏による特別講演「これからの物流センターはどうあるべきか」が開催されました。
人口減少や技術革新、異業種との競争激化など、物流業界を取り巻く環境変化を踏まえ、装置型センターの設計、データによる遠隔管理、標準化の重要性などが語られ、観客にとって深い示唆を与える内容となりました。 本発表会は、同協会が主催する改善ソリューション委員会の活動成果を広く共有する場として企画されたもので、物流事業者、システムベンダー、施設デベロッパー、人材サービス企業など、多様な業界関係者が一堂に会しました。また、経済産業省からもご来賓として参加いただき、官民連携による物流業界の革新に向けた期待と意義を改めて感じる場ともなりました。

委員会活動の集大成(成果発表)
委員会は4つのワーキンググループ(WG)に分かれ、物流現場の課題に対するソリューションを研究・提言した発表を行いました。
WG1:人材関連
テーマ:「人的資産の共有 ~人材確保のための共通プラットフォーム~」
内容:採用・育成・定着に関する課題と解決策を整理。物流業界が直面する深刻な人材不足と
若年層の定着率の低さに対応するため、統合型採用プラットフォームを展開し、多様な
人材の活躍の場を広げながら、業界全体のスキル向上・効率化・雇用の安定化を図り、
持続可能な社会と経済に貢献することを目指しました。

WG2:立ち上げ方法論
テーマ:「センター立ち上げ・設備やシステム導入の失敗を防ぐには」
内容:物流センターの立ち上げや設備・システム導入における28件の失敗事例を詳細に
分析し、特に「目的・目標設定の不備」「要件定義の不足」「運用設計の未整備」が
失敗の主因であることを特定しました。これらの教訓をもとに、現場を巻き込んだ
綿密な計画立案と、段階的な導入プロセスを推奨する導入ガイドブックとチェック
ポイントマップを作成し、物流現場における投資リスクの最小化と成功率の向上を
目指す方法論を体系化しました。
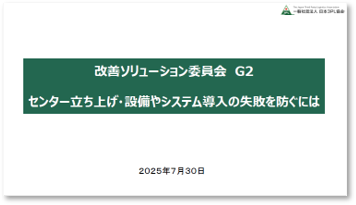
WG3:ソリューション連携
テーマ:「2050年に向けた持続可能な物流社会の実現 ~2030年迄のアクションプラン~」
内容:2050年に向けた持続可能な物流社会の構築を目指し、脱炭素・レジリエンス・労働力
安定の3要素を同時に実現する物流ネットワークの必要性を訴えました。
その実現に向けて、現場起点で取り組める改善策として「小さく始めるDX」
「企業・システム・データの連携」「若手人材育成」の3つのアクションを提示。
特に、アナログ業務のデジタル化による業務効率化、企業間のデータ統合による配送
最適化、Z世代の価値観に寄り添った柔軟な働き方の提案など、現実的かつ未来志向の
施策を通じて、物流業界の持続可能性と社会的価値の最大化を図る方針を示しました。

WG4:物流施設関連
テーマ:「物流施設における職場環境の課題と展望」
内容:物流施設の労働環境における課題として、人手不足と熱中症リスクが深刻化していま
す。全国3,000人規模のアンケート結果を踏まえ、快適な職場環境、とりわけ空調設備
の整備が人材確保・定着率の向上に直結すると提言。
現行補助制度では新設空調への支援が不十分であるため、建設時・改修時の助成制度や
電気代負担の軽減など、空調を標準設備として導入できる仕組みづくりが求められてい
ます。
産官民が連携し、持続可能な物流施設の在り方を再構築することが今後の業界発展に
不可欠であることを発表。
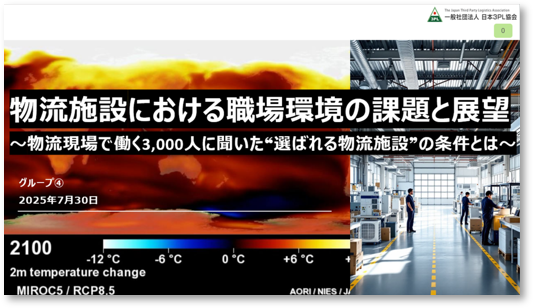
各WGの発表は、現場のリアルな課題に根差したものであり、参加者からは「すぐに現場に活かせる内容だった」「他社との連携のヒントになった」といった声が多数寄せられました。
特別講演:「これからの物流センターはどうあるべきか」
講師:センコーグループホールディングス株式会社 専務執行役員 藤田浩二氏
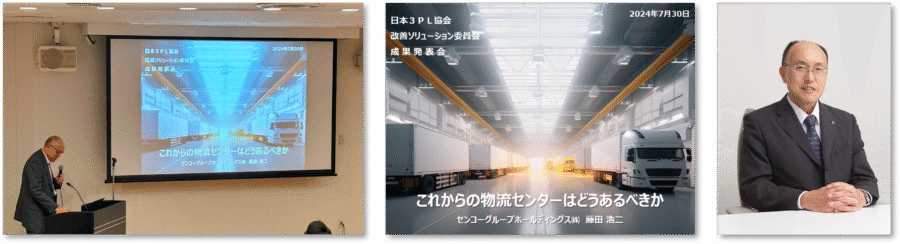
物流業界が直面する人口減少・高齢化・技術革新といった地殻変動を背景に、今後の物流センターのあるべき姿について多角的な視点から示唆がなされた。
藤田氏は、「荷主の指示に従うだけでは今後、生き残ることは難しい」と強調。マーケティング力や価格戦略の欠如は、サービスの無償提供・長時間労働・生産性の低下を招き、結果として企業の競争力が弱体化すると警鐘を鳴らした。
また、2030年には物流ロボティクス市場が現在の8倍以上に成長する見込みであることから、センター設計段階からロボットや装置の導入を前提に構築する「装置型センター」の必要性が示された。とりわけ、荷姿や商品の特性に応じてセンターを分類し、標準業務フローや業務タイムの設計を進めることで、デジタル技術による遠隔管理や省人化を実現し得るとした。
さらに、競争相手は同業他社だけでなく、テクノロジー企業や異業種が台頭する時代において、業界は「標準化・データ化・装置化」の三位一体を軸に、持続可能で価値ある物流センターの創造を急務とする未来像を提示した。10年後の“当たり前”を再考する視点が、参加者に強い印象を残した講演となった。
まとめ
今回の「改善ソリューション委員会成果発表会」は、物流業界の未来に向けた活発な議論と知見の共有が行われ、参加した観客の多くから高い評価と共感を得ることができました。
特に、各WGによる提言は、現場のリアルな課題に向き合いながらも、革新性や将来への展望を持った内容で構成されており、参加者にとって深い学びと刺激となりました。
・人材の確保と活用に対する実践的な視点
・設備導入や施設立ち上げに関する失敗回避の手法
・ 2050年を見据えた物流社会へのアクションプラン
・空調環境改善に焦点を当てた快適で“選ばれる”施設づくり
講演者それぞれの熱意や専門性が光る中で、物流の新たな可能性を共有できたことは、今後の委員会活動や業界連携において大きな礎となるでしょう。
物流を支える人々が集い、共に学び、未来を描いた一日で、この成果発表会は、まさに“現場から生まれるソリューション”が社会を動かす力となることを実感できるイベントとなったでしょう。